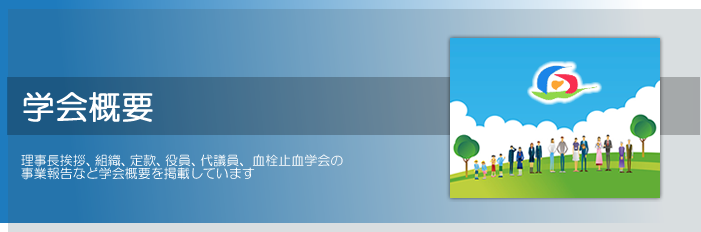
 この度、日本血栓止血学会の理事長を拝命いたしました奈良県立医科大学血液内科・輸血部の松本雅則と申します。歴史と伝統のある本学会の理事長に選んでいただき、身の引き締まる思いです。本学会がさらに発展できるように努力してまいります。
この度、日本血栓止血学会の理事長を拝命いたしました奈良県立医科大学血液内科・輸血部の松本雅則と申します。歴史と伝統のある本学会の理事長に選んでいただき、身の引き締まる思いです。本学会がさらに発展できるように努力してまいります。
ポストコロナの時期になり、同時に日本も大きな曲がり角に来ているように思います。本学会も否が応でも変わらざるを得ない時期に来ているものと思います。本学会は、歴史的に基礎研究に重きを置いて発展してきましたが、近年新規薬剤などの開発に伴い臨床研究も活発になってきました。ただし、これは血栓止血領域に限ったことではありませんが、日本全体の学問レベルの相対的な低下が指摘されています。様々な原因が指摘されていますが、主たる理由として研究費と研究時間の減少ではないかと考えます。これを改善するのは簡単なことではありませんが、まずできることから開始したいと思います。
理事長就任にあたり、上記の問題を含めて当面の4つの課題を掲げました。
1.研究レベルの向上
研究費の減少に関して、製薬企業からの奨学寄付金がほぼ無くなり、公的研究費も限られる中、本学会が行っております研究費助成事業をさらに発展させたいと考えています。また、働き方改革の中で個人の研究時間を増やすことは難しいですが、研究者の人数を増やすことで研究レベルを上げることはできると考えます。新しい仲間を増やすという意味では、毎年実施している教育セミナーは良い取り組みだと思います。ただし、新人のリクルートには限界があると思いますので、他分野とのコラボにより仲間を増やすことを考えたいと思います。国際血栓止血学会などには、循環器、脳神経、肝臓、産婦人科などの多彩なバックグランドの方が参加しています。他学会とのコラボすることで学会員を増やすとともに研究レベルの向上にもつながるものと考えます。
2.女性会員の活躍
女性の活躍は、古くて新しい問題です。日本では私が医師になった30年前から女性の時代と言われていましたが、遅々として進んでいないと感じています。海外、特にヨーロッパの研究者の女性の割合が多いのは日本と大きく異なっており、国の代表として女性が活躍されていることも決して珍しくありません。本学会も決して女性の会員が多いとは思いませんが、発表などで女性が登壇されていることは珍しくありません。それが、その後の活躍につながっていないのが課題だと感じています。本学会では岡本賞Utako Awardを女性に授与していることは評価できると考えています。根本的な解決策は簡単ではありませんが、委員会のトップを女性が就任するなどの積極的に役職についていただくことも必要でしょう。さらに、女性会員を増やすためには、内科学会などで実施されている総会時の託児所サービスなど細やかな対策を考えていきたいと思います。
3.学会の社会貢献
能登半島地震は元旦夕方に発生したにもかかわらず、松下前理事長および関係者のご尽力により本学会から速やかに情報が発信されました。具体的には1月1日には関連学会とともにエコノミークラス症候群に関する声明を出し、続いて1月2日には「被災地における肺血栓塞栓症の予防について」という文章を本学会単独で発出しました。このような学会外、特に一般市民に対する活動は、学会として学術活動とともに重要であり、学会のもう一つの存在意義であることを再認識しました。このような災害に速やかに対応するためには、普段から準備しておくことが必要で常設の委員会を設置し、速やかに情報を発信できるように準備していきたいと思います。その他に、学術総会の際に開催される「市民公開講座」の他に、「世界血栓症デー」「世界血友病デー」の取り組みなど一般市民への講演会は、本学会の認知度の向上には重要だと考えています。
4.国際化
これも当学会だけの問題ではありませんが、日本国内では内向きの傾向が強く国際化の問題があります。日本からの国際学会への参加者の減少や海外への留学者も減っている状況です。コロナ以外にも、歴史的な円安、日本がデフレ傾向であったことなどが主たる原因かもしれませんが、若者の海外志向が強くないように感じます。海外留学助成に加えて、国際学会参加の助成などを創出したいと考えています。また、国際血栓止血学会や学術標準化委員会(SSC)などの運営、企画に積極的に参加することで、日本の存在感を高めていきたいと思っています。
これらの4つの課題については、すぐに解決できるものではありませんが、本学会の将来にかかわる重要な項目だと思います。少しずつでも前に進めていきたいと考えています。私は強力なリーダシップを発揮する人間ではないと認識しております。学会内外の方々からの協力を仰ぎながら学会運営を行っていきたいと思いますので、ご指導・ご協力いただけましたら幸いです。
一般社団法人日本血栓止血学会
理事長 松本雅則
本学会は、生体防御の一環として重要な止血機構と心筋梗塞や脳梗塞などの病因である血栓症を基礎から臨床まで幅広く研究する。
歴史的には血液凝固、血小板、出血性素因などの臨床的研究から始まり血液学の一分野であったが、過去20年間に分子生物学、細胞生物学の応用と血管系の研究により急速に成長し、現在では生化学、生理学、脈管学、循環器学、小児科学、外科学、産婦人科学の研究者から成る横断的、学際的性格の強い学会である。我が国でも食生活の欧米化ならびに高齢社会を迎えて虚血性心疾患や脳血管障害などの血栓性疾患が著しい増加傾向にあり、その病因病態の解明、治療、予防などを目標とする。
1978年4月
約1,200名
基礎系・臨床系の医学研究者および薬学、理学系研究者
| 【理事長】 | 松本雅則 |
| 【副理事長】 | 森下英理子 |
| 【理 事】 | 渥美達也 池添隆之 伊藤隆史 井上克枝 大森 司 小亀浩市 後藤信哉 関 義信 野上恵嗣 橋口照人 藤井輝久 山本晃士 横山健次 |
| 【監 事】 | 岡本好司 松下 正 山崎昌子 |
〒112-0013
東京都文京区音羽1-17-11 花和ビル405号室
電話 03-6912-2895 FAX 03-6912-2896
ホームページ:http://www.jsth.org/
「日本血栓止血学会誌」隔月
第47回日本血栓止血学会学術集会
会期:2025年6月27日(金)~6月29日(日)
会場:ウインクあいち
会長:松下 正 名古屋大学医学部附属病院 輸血部
第20回 SSCシンポジウム
会期:2026年2月14日(土)
会場:野村コンファレンスプラザ日本橋
会長:奥 健志 東海大学医学部 リウマチ内科
第13回 教育セミナー
会期:2025年11月8日(土)~9(日)
会場:クロス・ウェーブ梅田